
こんにちは、えばと申します。
この記事をお読みいただきありがとうございます。
今回の記事は主に、
- 新卒の就活生
- 既卒生
- 社会人の方
- これから就活を控えている方
などの方にぜひ最後までお読みいただきたいです。
あなたは、
「大学・専門学校を卒業したら就職するのが当たり前」
という考えについてどう思いますか?
おそらく多くの方は特に疑問には思わないでしょう。
世の中の大半の人は新卒で就職します。
高校、大学、専門学校を卒業すると同時に社会人になります。
就職するのは大前提として、
「民間企業に就職するか、公務員になるか」
と迷う、迷った方が大半です。
僕自身も新卒就活時、この2択は大きく迷いました。
ブログを始めてからというもの、多くの方に
「そんなことやってないで早く就職しろよ」
と言われてきました。
では、本当に新卒生は就職しなければいけないのでしょうか?
就職が全てでそれ以外の選択肢はないのでしょうか?
今回の記事では、
「新卒すぐに正社員になるのはそんなに重要か?」
という点についての僕の意見をお話し、
「就職以外の選択肢とその現実的な問題」
を考察していきます。
ぜひ最後までお付き合いいただけたらと思います!
新卒後すぐに就職するのはそんなに重要?
僕の意見
僕としては、就職せず他の道に進むという選択はありだと思っています。
「これからは個の時代だ」
などと聞くことも増えてきました。
ただ、あなたが
- 今何か夢を追っている人
- どうしてもかなえたい夢や目標がある人
- 今何かで少しでも成果を出せている人
- やってみたいことが明確にある人
ではない場合、今は一度就職することをお勧めします。
就職し正社員になると、何事もなければ毎月安定した収入を得られ、ボーナスももらえます。
また正社員は社会的信用も高く、ローンを組んだりクレジットカードを作る時に不自由があまりありません。
就職した企業の元、何か一生モノのスキルを身につけられるかもしれません。
就職し正社員になるということには、多くのメリットが存在しています。
そのため、上記の特徴に当てはまらない人は一旦就職することをお勧めします。
上記の特徴に1つでもあなたが当てはまるのであれば、就職しないのはありだと思います。
就職しなかったことで何か失敗をしたり、後悔をすることもあるかもしれません。
それでも、就職しないという道を進んだからこそ得られる経験もあるでしょう。
どれだけ頑張ってもお金を稼げないものもあります。
心が折れたりするときもあれば、何とも比べ物にならないくらいの喜びを感じる時もあるでしょう。
そういった時が来ることを覚悟し、自身の行動に責任を持てるのであれば、就職しない選択はありです。
正直今の日本では「新卒カード」はとても重要です。
これを捨てるという選択をする以上、今後就活をするときには苦労するかもしれません。
ただ、今後一切就職できなくなるわけではありません。
自分の追いたい夢や目標に向けて努力し、無理だとなれば諦めて就職することもできます。
何かをして失敗して後悔するより、何もしなかった後悔のほうが大きいです。
夢や目標があるなら、そこに覚悟と責任を持ち頑張ってください。
就職以外の選択肢と現実的な問題
ここからは、
「実際に就職をしない場合にどういう選択肢があるか」
をご紹介し、
「その選択肢の現実的な問題」
について触れていきます。
僕の想像も多少含まれるかもしれませんが、ご了承いただけたらと思います。
①フリーランスや個人事業主になる

就職以外で考えられる選択肢1つ目は、フリーランスや個人事業主になることです。
フリーランスとは、
「実店舗がなく、雇人もいない自営業や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」
と経産省が定義しています。
(※参照:https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201224007/20201224007-2.pdf)
個人事業主もフリーランス同様、企業や団体には所属せず、独立して事業を営む人のことです。
個人事業主の場合は、「開業届」というものを税務署に提出する必要があります。
「これからは個の時代」
なとど言われるだけあり、フリーランスや個人事業主になる人は毎年数を増やしています。
2021年時点では、日本のフリーランス人口は1577万人もいるそうです。
(※参照:『新・フリーランス実態調査 2021-2022年版』発表 | ランサーズ株式会社コーポレートサイト (Lancers,Inc.))
AIが発達し、人間がする仕事は確かに減っていくことでしょう。
そういう状況になった時、自分で稼げるスキルや術を持っていることは重要だと思います。
何かスキルを身につけて、そのスキルを活かし生計を立てる。
働く時間や場所に縛られず、マイペースに働ける。
こういうイメージがあり、憧れる気持ちはわかります。
ただ、フリーランスはそんなに甘いものではありません。
そもそもフリーランスや個人事業主になる人の多くは、
「企業で1度以上働き、スキルや経験・知識を少しでも持つ人」
です。
働いている中で得たスキルや経験・知識を活かし個人で働く。
こういった人が多いので、新卒間もない人が飛び込むのは少し難しいです。
フリーランスや個人事業主になるのは誰だってできますが、それで生計を立てるのはなかなか厳しいです。
フリーランスの方々は自身のスキルや経験を活かし、案件を勝ち取ります。
そしてその受けた案件の成果物を納めて、収益を得ています。
新卒間もない人にとって一番難しいのは
「自身のスキルや経験を活かし案件を勝ち取る」
という部分です。
何もスキルも経験もないという場合、そもそも案件を受けること自体難しいです。
結果いつまでたっても収益は0…。
こういう状況に陥る可能性が高くなってしまいます。
「就職していれば、月10万は少なくとももらえていたのに…。」
と後悔することもあるでしょう。
また、社会的信用もいまだに低いという現状があります。
そのため、銀行でローンを組んだりクレカを契約することも難しくなります。
経済的な不況があれば、真っ先に契約を切られるのはフリーランスです。
いきなり収入が減り、生活が一気に苦しくなる時もあるかもしれません。
こういったことをまず理解してください。
それでもフリーランスや個人事業主になるという覚悟があるのなら、挑戦してみてもいいと思います。
僕の個人的な意見としては、一度就職してスキルや経験を得てからでも遅くないのかなとは考えています。
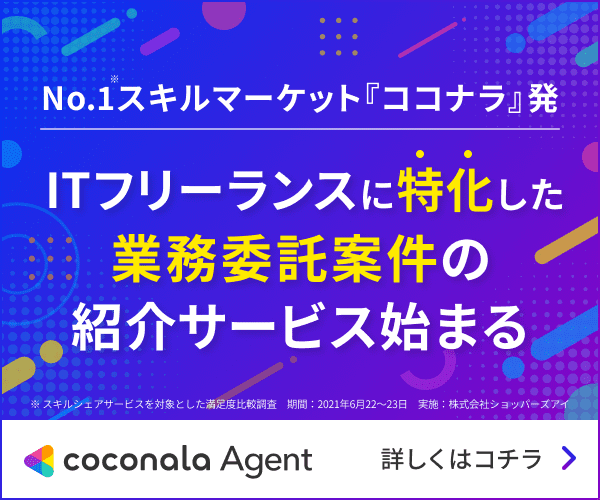

②アルバイトやパートなど非正規雇用で働く

就職以外で考えられる選択肢2つ目は、非正規雇用として働くことです。

アルバイトやパートであれば、働いた分だけお金がもらえます。
働く時間によっては、月15万円以上稼ぐこともできるでしょう。
アルバイトやパートに関わらず、従業員は1日8時間、週40時間の労働上限を労基で定められています。
時給1000円だとして、週40時間、月160時間働いたら月収16万円。
(実際はここから税金が引かれるのでおそらく14万前後になるでしょう)
これだけもらえたら結構普通に暮らせるじゃんと思う方もいると思います。
もしあなたが一人暮らしをする時が来たとき、アルバイトやパートだと少し苦労するかもしれません。
まず社会的信用面で、アパートを借りる時に苦労するときもあるでしょう。
また、パートの収入のみだとなかなか贅沢はできません。
アルバイトやパートの苦しいところは、一般的にボーナスがもらえない点です。
正社員であれば、多くのところでボーナスが1回以上支給されます。
企業によっては3回以上貰えるところもあります。
厚労省の調査によると、2021年夏のボーナス支給額は平均380268円、冬のボーナス平均は380787円だったそうです。
(※参照:毎月勤労統計調査 令和4年9月分結果速報等|厚生労働省)
ボーナスの平均支給額は基本給の1-2か月分とも言われています。
これが支給されるのとされないのとでは大きな違いになってきます。
パートの人の平均月収は99939円だそうです。
(参照:毎月勤労統計調査 令和4年9月分結果速報等|厚生労働省)
これを年収にすると119万9268円です。
国税庁の調査によれば、20代前半の正社員の人は平均月収が269万円、20代後半の人は平均358万円だそうです。
(※参照:1 平均給与|国税庁)
新卒の方の場合、多くは20-22歳の人でしょう。
パートで働くと年収が約120万円、正社員だと約270万円。
この差はとても大きいです。
それでもいいという方であれば、パートやアルバイトで働くという選択はありでしょう。
ただ、個人的には就職するまでのつなぎとして考えたほうがいいのかなと思っています。


③芸能人やYouTuberなどの「タレント業」

就職以外で考えられる選択肢3つ目は、「タレント業」を目指すことです。
ここでは、
- 芸能人
- YouTuberなどの配信者
- TikToker
などなどをまとめて「タレント業」ということにします。
こういうタレント業の人達はすごく華やかに見えますし、羨ましく思う時もあります。
タレント業界を夢見る人は多いのではないでしょうか?

僕自身も短期間ではありますが、芸能事務所に所属しレッスンなどを受けていた時期がありました。
この選択肢は誰に言われるでもないでしょう。
めちゃくちゃ厳しいです。
あなた自身に華があったり面白かったり、何か他者と比べて光るものがあれば別ではあります。
ただあまり自分に自信がなかったり、メンタルが弱かったりする場合はなかなか厳しいと思います。
タレントデータバンクに登録されている芸能人は現在24000人ほどいます。
「芸能事務所に所属している人」だとこれよりもっと多くの人がいます。
その中で芸能界の仕事のみで生計を立てている人はごくわずかです。
YouTuberも現在数えきれないほどいます。
その中でYouTubeのみで生計をたてられている人は、1割にも満たないでしょう。
先述したフリーランスや個人事業主より、タレント業で生計を立てることは難しいです。
タレント業は誰でも始めることができるものではあります。
芸能界を目指す場合は、事務所のオーディションに応募したり、大きなオーディションイベントに応募することになります。
ただ、事務所には入ったものの一生売れることなく辞めてしまう人がたくさんいます。
YouTuberも同様です。
誰でも始められますが、結局何もうまくいかずに辞めてしまう人がたくさんいます。
「強い覚悟」と「強靭なメンタル」。
この2つがある人は一度挑戦してみてもいいとは思います。
やらないで後悔するくらいなら、全力でやってから後悔しましょう。
何事も挑戦しないことには成功はありません。
「自分はどうしても頑張ってみたいんだ!」
という強い気持ちがあるなら、一度足を踏み入れてみてもいいと思います。


④起業する

就職以外で考えられる選択肢4つ目は、起業です。
「起業はさすがにハードルが高すぎる…。」
「あまりにも無謀ではないか」
と感じる方もいるかもしれません。
確かに僕自身起業したことはありませんし、起業家の友人もいません。
そのためここでは「主観」ではなく「事実」に基づいてお話していきます。
起業とは、
「自身が経営者として事業を立ち上げ、事業や企業を運営していくこと」
です。
昔は高額な資本金がないと株式会社を設立できない、という法律がありました。
(資本金1000万円以上、旧商法)
ただ2006年に会社法が改正され、資本金の最低ラインが撤廃されました。
結果、2022年現在は資本金がたったの1円でも会社を設立できるようになっています。
起業のハードルは低くなりました。
ただ、やはりそう簡単にできるものではありません。
「社長とかかっこいいし起業してみよう!」
くらいの気持ちではなかなかうまくいかないでしょう。
起業するにあたって様々な手続きが必要ですし、何よりも
「どういう事業をしていくのか」
がとても重要になります。
起業をもしするのであれば、学生のうちからいろいろ考えておいた方がいいです。
学校を卒業した後、
「さて、どんな事業をしようかなあ」
と考えるのでは少し遅いです。
せっかく起業の意志があるなら、今のうちから起業に関することを調べておきましょう。
今までの選択肢と同様、
「新卒カードを失う」
ということはデメリットにはなります。
転職活動をするときに少し苦労することもあるかもしれません。
「それでも自分はやるんだ!」
という強い意志があるのであれば、一度挑戦してもいいと思います。
苦しいこともあるとは思いますが、そこでしか得られない経験や喜びもあるでしょう。
まとめ
今回の記事では、就職しないことに関する僕個人の意見と、就職以外の選択肢についてお話してきました。
いかがでしたでしょうか?
現在の日本では、大学や専門学校を卒業したら就職するのが普通だと言われています。
「新卒カード」という言葉もあるように、新卒というのは人生で一番就職しやすいタイミングです。
これを逃すと、就職したいとなった時に少し苦しくなるかもしれません。
またこういう現状なため、就職しないとなると誰かから心もとないことを言われたり、無理だと言われることもあるでしょう。
それでも、あなたの人生はあなたのものです。
ご両親や友人、先生、親戚の方々などのものではありません。
そのため、自分が後悔しない選択をするようにしてください。
特に理由もなく夢や目標を諦めると、いつか必ず後悔する日が来ます。
何もしなかったことを悔やむくらいなら、何か挑戦に失敗してから後悔しましょう。
挑戦しないことには成功も失敗も得られません。
一度きりの人生、後悔しないような選択をしてください。
今回の記事を通し、
「やっぱり自分は就職しよう」
と思った方もいるかもしれません。
その選択も僕は決して間違いではないと思います。
就職活動は大変なものではありますし、気を病みそうなときも来るでしょう。
そういう時はまず休むようにしてください。
僕は全く休まずに就活を続け、結局何もうまくいかなくなってしまいました。
就活は今も頑張ろうとはしていますが、なかなか一歩踏み出せていない状況です。
こうなってしまう前に、絶対に休んでください。
休んだ後、
「もう一回頑張ってみよう!」
と思えたら、その時はまた頑張りましょう。
あなたの就職活動がより良いものになるよう、心から願っています。
www.ebablog.jp
せっかくの人生、後悔の無い選択をしていきましょう!
今回は以上です。
最後までお付き合いいただきありがとうございました!
またほかの記事もお読みいただけたら幸いです!

にほんブログ村
www.ebablog.jp
www.ebablog.jp
www.ebablog.jp





































